はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をしているれんれんです♪
今回は、私のクラブで子ども達が大盛り上がりだったユニークな遊び、「全滅鬼ごっこ」をご紹介します!
「全滅鬼ごっこ!?なにそれ?」と、初めて聞いたときの子ども達は興味津々。ルールもすぐに覚えて、笑顔いっぱいで楽しんでくれました♪
🌟 この遊びが人気の理由とは?
子ども達にとって、「ただ走る」だけでは物足りなくなってくる時期があります。そんな中、ゲーム性や頭脳戦の要素が加わった遊びは、新しい刺激として受け入れられやすいです。
特に高学年の子ども達は、「次はどの番号を狙うべき?」「あの子の動き怪しいな…」と、まるで戦略ゲームのように仲間と考えながら動いていました。
🎯 対象年齢
小学生全学年に対応しています!
低学年でもルールが簡単で、みんなが主役になれる遊びです。
👨👩👧👦 必要な人数
6人以上でプレイ可能!
10人以上だとより盛り上がります♪
🎒 準備物
- ビブス(チーム分けが分かりやすくなります)
- トランプ(番号&ジョーカー用)
🎮 全滅鬼ごっこのルール
🔑 基本ルール
- 制限時間は10分(目安)
- 2チームに分かれて行う
- 各チームの「鬼」は1人(途中交代OK/ハイタッチで交代)
- 鬼以外の子はトランプ番号(1〜人数分)を持つ
- 鬼はジョーカーを持ち、相手チームを順番通りに捕まえる
- タッチされた子は、鬼に自分の番号を見せる(順番が違えば逃げてOK)
- より多くの番号を順番通りに揃えたチームの勝利!
🔄 応用ルールでさらに盛り上がる!
- 鬼を2人に増やす(ジョーカー2枚)
- トランプ番号を2桁にする(例:1〜20)
- 特定の番号だけを狙う「スナイパー戦」も面白い!
人数が多いクラブや学童では、チームを増やしてトーナメント形式で行うと、一日中楽しめますよ!
🚨 安全に遊ぶポイント
室内でも安全に遊べます!ただし、次の点には注意が必要です。
- 階段・段差には近づかないように誘導
- 走りすぎ防止のため、スキップや早歩きでの移動をルールにする
🧠 育つ力いろいろ!
ただの鬼ごっこではなく、「順番に捕まえる」「番号を記憶する」「仲間と相談する」要素が入っているので、子ども達の様々な力を育てます!
👀 支援員の立場からのアドバイス
初めて遊ぶときは、鬼役を職員や高学年が最初に担当して見本を見せるのがおすすめ。見て学ぶことで、低学年もスムーズにルールを覚えてくれます。
また、鬼が番号順に狙うルールは難しく感じる子もいるので、はじめは「好きな順」→慣れたら「順番制」というステップアップ方式も効果的です。
こうした段階的な支援があることで、子ども達全員が成功体験を得やすくなり、自信にもつながります。
遊びながら「できた!」「伝えられた!」「考えた!」を積み重ねていけるのが、全滅鬼ごっこの魅力です。
🗣 実際に遊んでみた感想
クラブで初めて実施した日は、想像以上の大盛り上がり!
子ども達は「チームで戦う」ことにワクワクし、鬼を誰にするか相談したり、逃げ方を話し合ったり、まさに遊びながら学んでいる様子でした。
特に印象的だったのは、低学年の子が高学年に「次、○番が残ってるよ!」と声をかけていたこと。自然とコミュニケーションが生まれていたのが嬉しかったです。
🪄 最後に:遊びを日常に取り入れるヒント
遊びには、子どもの成長に欠かせない学びが詰まっています。だからこそ、「ただ楽しい」だけで終わらせない工夫が大切。
この全滅鬼ごっこは、まさに「遊びの中で育つ力」が実感できるアクティビティです。ぜひ、みなさんの児童クラブやレクで活用してみてくださいね!
📝 まとめ
今回は、「全滅鬼ごっこ」というちょっと珍しい鬼ごっこをご紹介しました!
鬼ごっこ×チーム戦×頭脳プレイという要素が組み合わさって、学年問わず夢中になれるおすすめの遊びです。
室内でも屋外でも応用可能なので、ぜひ放課後児童クラブやレクリエーション活動で取り入れてみてくださいね!
🔗 他にも楽しい遊びを紹介中! → 鬼ごっこ特集はこちら



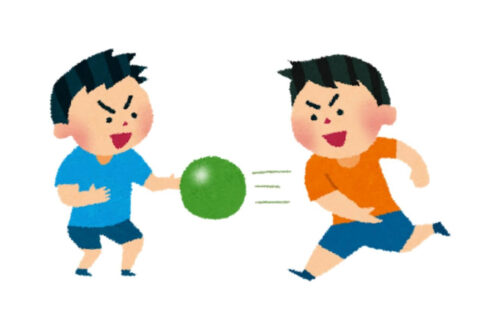




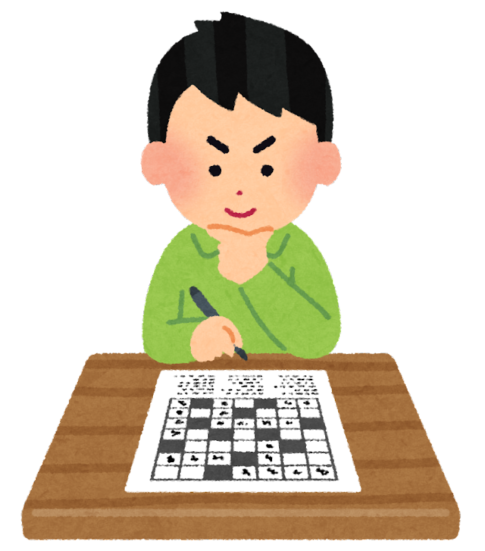
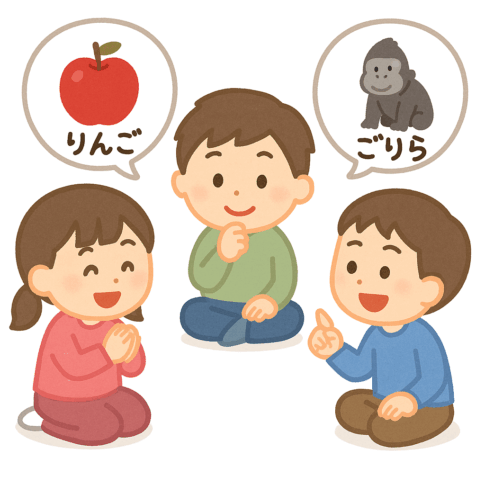





コメントを残す