はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をしているれんれんです♪
今回は、私のクラブで子ども達に大人気だった言葉遊び、「区切りますゲーム」をご紹介します!
最初は「なにそれ?」と不思議そうだった子ども達も、いざ始めてみると大爆笑!
「もう一回やりたい!」「次は長い言葉にしよう!」と、何度も繰り返して遊ぶほどハマってくれました。
ルールも簡単で道具も少なく、言葉をリズムよく区切ってつなげるだけの遊び。
低学年でもすぐに参加でき、自然と語彙力や表現力も育ちますよ♪
🎯 対象年齢
小学生全学年におすすめ!
ルールがシンプルなので、低学年でも安心して楽しめます。
👥 必要人数
2人以上いればすぐに遊べます。人数が多いほど盛り上がります!
🎒 準備物
- お題カード(あらかじめ言葉をいくつか準備しておくとスムーズです)
🎮 ルール(動画あり)
※動画では再生後すぐに遊びの様子が見られます
🔑 基本ルール
お題の言葉を途中で自由に区切って、リズムに合わせて次の人に繋いでいくゲームです。
- 例:「クリスマス」というお題
- 1人目:「クリス」
- 2人目:「マス」
- 3人目:「クリスマ」→ 4人目:「ス」…のように繰り返す
- うっかり全部の言葉を言ってしまったら、その次の人は「イエイ!」と言って流れをつなげます
- 言い間違い、詰まった、リズムが崩れたらアウト(罰ゲーム・交代などルールは自由にアレンジOK)
🧠 この遊びで育つ力
「区切りますゲーム」は、言葉を扱う遊びの中でも特に想像力や反射力、表現の柔軟性を育てるのにぴったりです。
このように、ただの言葉遊びのように見えても、子どもの発達や学びにつながる要素がたくさん詰まっているんです。
学童保育や放課後クラブでは、日々のレクリエーションの中で「楽しい+学びになる遊び」を取り入れることがとても大切。
この「区切りますゲーム」は、まさにそんな実践にぴったりな活動です。
支援員としても、子ども達の遊びの様子を観察しながら、「この子は語彙が豊かだな」「反射的に言葉を返すのが得意だな」といった一人ひとりの個性や成長を感じられる瞬間が多い遊びでもあります。
🚨 安全面の配慮
身体を動かさない座り遊びなので、ケガや事故の心配はほとんどありません。
ただし、周囲で動いている子がいる時は、静かなスペースを確保するか、時間を区切って行うのが◎。
🗣 実際に遊んでみた感想
「こんな簡単な遊びでこんなに盛り上がるんだ!」と驚いたのが正直な感想です。
区切り方でリズムがズレたり、笑いが起きたりと、子ども達の発想力に毎回感心します。
特に盛り上がったのは、難しい長い言葉(例:「ディズニーランド」)をあえて選んだとき!
「ディズ」「ニー」「ランド」など予想外の区切り方に、笑いと拍手が起こりました。
📝 まとめ
今回は、言葉をリズムよく区切ってつなげていく「区切りますゲーム」をご紹介しました。
道具いらず、ルール簡単、でも脳トレにもなる万能な言葉遊びです。
学年を問わず楽しめて、ちょっとした空き時間や雨の日のレクにもぴったり!
ぜひ、児童クラブや学童保育の現場で取り入れてみてくださいね♪
📚 他にも言葉遊びを紹介中 → 絵しりとりの記事はこちら


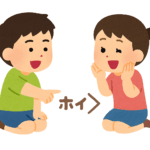

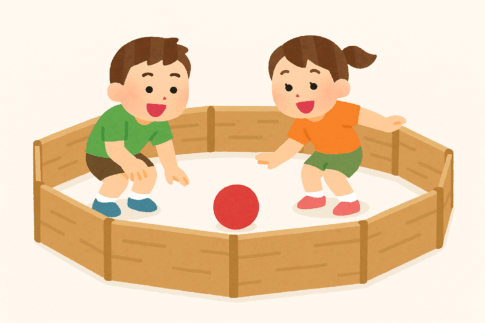











コメントを残す