はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をしているれんれんです🌺
放課後の活動って、ついつい「いつもの遊び」にマンネリしがちですよね。でも、そんなときこそ取り入れてほしいのが今回ご紹介する「二人三脚鬼ごっこ」です🏃♂️🏃♀️
これは、ただの鬼ごっこと違い、ペア同士の絆や声かけの力が試されるユニークな遊び!お互いの足を結びながら逃げたり追いかけたりすることで、運動能力・協力性・判断力など、多くの力が育まれます。
「あー、そっち行こう!」「スピード合わせてー!」なんて、子どもたちの真剣で楽しそうな声が飛び交うこの遊び。導入も簡単で、低学年~高学年まで幅広くアレンジ可能なのもポイントです✨
今回は、そんな二人三脚鬼ごっこのルールや魅力、支援のポイントまでをたっぷりご紹介します!
🎮 どんな遊び?ルールをチェック!
二人三脚鬼ごっこは、その名の通り「二人三脚」と「鬼ごっこ」が合体した遊びです。
- 2人1組でチームを作り、片足ずつをひもで結んで二人三脚の形にします。
- 鬼チームを1組決め、他のペアは逃げる役になります。
- 鬼は二人三脚のまま逃げるペアを追いかけ、タッチされたペアが新たな鬼に。
- 一定時間で最も長く逃げ切れたペアの勝利です!
👦 対象年齢・人数
小学生全学年におすすめですが、低学年はサポートありで安全に実施しましょう。
人数は4人〜12人程度が最適。大人数の場合は複数グループに分けてリレー形式にしても楽しいですよ!
🌱 育まれる力と学年別支援
🌟 得られる力
- 🏃♂️ 運動能力:二人でバランスを取りながら走ることで、体幹・脚力・持久力がバランスよく育まれます。
- 🧠 判断力・連携力:進行方向や障害物を見て「どこに逃げる?」など、相談しながら判断する力が養われます。
- 🤝 協力性・信頼感:足が結ばれているからこそ、声かけ・思いやり・呼吸を合わせることが大切になります。
- 🎭 自己調整力:スピードやタイミングを相手に合わせて走ることで、焦らず冷静に動く力が育ちます。
🧒 学年別支援ポイント
- 低学年:コースは直線的で見通しのよい場所にし、ひもは幅広ゴムやマジックテープで転倒リスクを軽減。ペア練習タイムを設けて安心感UP。
- 中学年:障害物ゾーン(マット・コーンなど)を設けたり、「タッチで復活」などルールを工夫すると盛り上がりやすいです。
- 高学年:作戦タイムを取り、鬼チームで連携を考えるなど戦略性をプラス。「ペアチェンジゾーン」など発展ルールも効果的!
🛟 安全に楽しむためのポイント
- 足を結ぶひもは柔らかくて安全な素材(マジックテープやスカーフなど)を使用
- スタート前に「二人三脚の歩き方」を練習してからスタート
- 障害物のない平坦な場所を選び、靴ひもや段差にも注意しましょう!
🎉 おもしろポイント!
この遊びの最大の魅力は「協力しながら逃げるハラハラ感」!
いつもは個人プレーの鬼ごっこですが、足を結ばれていることで笑いが絶えません🤣
相手に合わせようとする気持ちや、転んでも笑い飛ばせる明るい雰囲気も魅力です。
🔗 関連記事
🍀 まとめ:楽しみながら育つ“二人三脚鬼ごっこ”の魅力
「二人三脚鬼ごっこ」は、協力・判断・バランス感覚を一度に育める、まさに全身で楽しむ“育ちの遊び”です。
足を結びながら走るというだけでもハードルはありますが、その分、仲間と声をかけ合ったり、呼吸を合わせたりする体験はとても貴重!活動を通して、子どもたちは「一人じゃない楽しさ」「相手を思いやる気持ち」を自然と学んでいきます。
さらに、年齢や発達段階に応じてルールを少しずつ工夫すれば、低学年〜高学年まで幅広く楽しめる万能レクリエーションになります。障害物ゾーンや作戦タイムを取り入れた高学年バージョンでは、戦略性やチーム戦の楽しさも引き出せますよ。
「最近ちょっと遊びがマンネリ気味…」というときには、ぜひ「二人三脚鬼ごっこ」を取り入れてみてください。きっと、子どもたちの笑顔と達成感あふれる声が響く、充実の放課後時間になるはずです😊


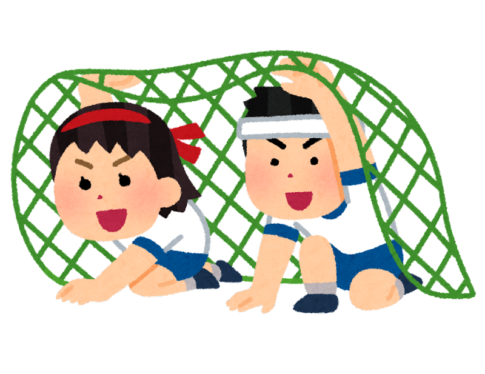






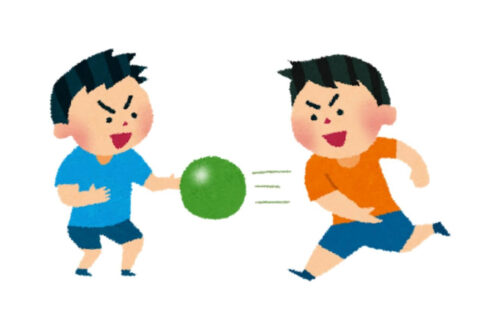





コメントを残す