はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をしているれんれんです🌞
放課後児童支援員の皆さん、子どもたちの「遊びたい!」という気持ちに応えながら、運動能力やチームワークも育てられる遊びを探していませんか?
そんな時におすすめなのが「ドッジビー鬼ごっこ」!
フリスビー型の柔らかいディスクを使って行うこのゲームは、ドッジボールのスリルと鬼ごっこのスピード感が融合した大人気アクティビティなんです✨
「フリスビーって当たって痛くないの?」「低学年でもできる?」という声も聞こえてきそうですが…安心してください!ドッジビーはスポンジ素材で安全性もばっちり👌
今回は、このドッジビー鬼ごっこのルールや魅力、支援のコツをたっぷりご紹介します!
運動量を確保しつつ、子どもたち同士のつながりや判断力も養える、まさに一石三鳥の遊びですよ🎯
🎯 ルール
鬼はドッジビー(布製の柔らかいフリスビー)を使って、他の子どもたちを狙います。
- ドッジビーを当てられた人が次の鬼になります(基本ルール)
- アレンジで鬼が増えていくバージョンもOK!
- フリスビーはキャッチしてもOKにするなど、子どもに合わせてルール調整が◎
👦 対象年齢・人数
対象年齢は小学生全般(6〜12歳)におすすめ!
人数は4人からOKですが、10人以上だと盛り上がり度MAX!広場や体育館で行うのがベストです。
🛡 安全面のポイント
- 柔らかい素材のドッジビーを使うことで怪我のリスクが少ない!
- 周囲に障害物がないか事前に確認
- 投げる際は顔や頭部を避けるように指導する
🌱 育まれる力と学年別支援
🌟 得られる力
- 🏃♂️ 運動能力:
逃げるときに素早く方向転換したり、投げるために助走をつけることで、全身の動きが鍛えられます。鬼の子も「どこから投げたら当たりやすいか」を体感的に学べます。 - 🧠 判断力・瞬発力:
「あの子、今こっちを見てない!」といった一瞬の判断で投げたり、逃げるタイミングを見極める力が養われます。
声かけ例:「今がチャンスかも!行けそう?」 - 🤝 協力性:
鬼チームでは「後ろから回ろう!」「あっちに逃げたよ!」など、仲間と情報共有しながら協力して追いかける場面が自然と生まれます。 - 🎭 切り替え力:
当てられて悔しくても、「よし!次はこっちが当てる番だね!」と前向きに切り替える練習に。
支援員の声かけがカギ:「鬼になっても楽しいぞ〜!」
🧒 学年別支援ポイント(より具体的に)
- 低学年:
・「当てていい場所」を支援員が最初に大きな絵で説明(顔はNG、お腹・背中はOK)
・近くからそっと投げる練習時間を用意
・逃げる子が緊張しすぎないよう「フリスビーが来たら止まってもOK」など配慮も◎ - 中学年:
・「◯分以内に何人当てられるかチャレンジしよう!」など制限時間ルールを導入
・「キャッチ成功で味方を1人復活」など、逆転要素を入れてドキドキ感アップ
・ルール決めを子どもたち自身に話し合いで任せても楽しい! - 高学年:
・作戦タイムを設定して、「どう追い詰める?」「誰がどのルートをふさぐ?」など、戦略性の高いやり取りが期待できます
・「ドッジビーを2枚同時使用」「逃げる子がペア行動」など、難易度UPアレンジでやりごたえ◎
🎉 ドッジビー鬼のここが面白い!
- ✅ フリスビーが空を飛ぶスピード感にみんな大興奮!
- ✅ 鬼ごっことドッジの融合で、新鮮で飽きない!
- ✅ 当てられても「次は鬼だ〜!」とポジティブな気持ちに切り替えやすい
- ✅ ルールをアレンジして「逆転のチャンス」も作れる!
🔗 関連記事もチェック!
📝 まとめ
ドッジビー鬼ごっこは、鬼ごっこ・ドッジ・フリスビーのいいとこどりの遊び✨
楽しいだけじゃなく、体力・判断力・協力性も自然と伸びていくのがこの遊びの魅力!ルールの工夫次第で年齢問わず楽しめるので、放課後児童クラブの定番レクとして大活躍間違いなしです。
ぜひ、子どもたちと一緒に「逃げて・当てて・笑って」大いに盛り上がってくださいね!





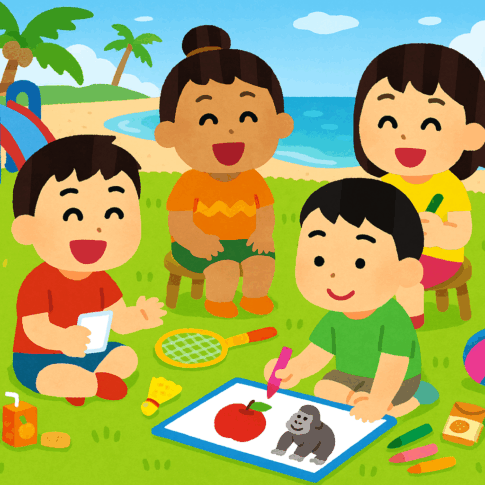
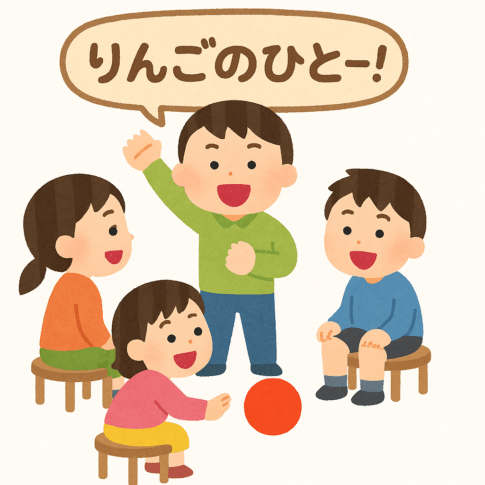
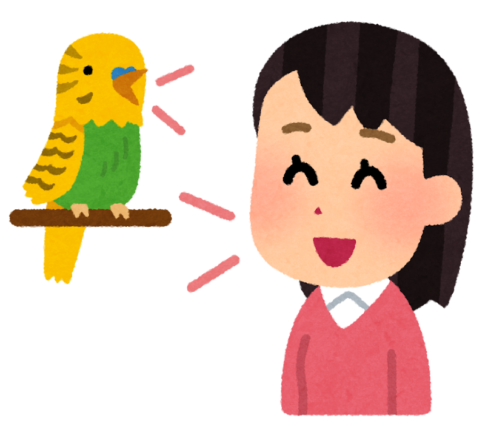
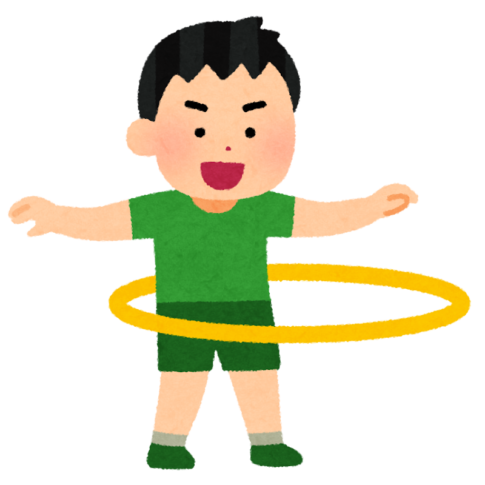

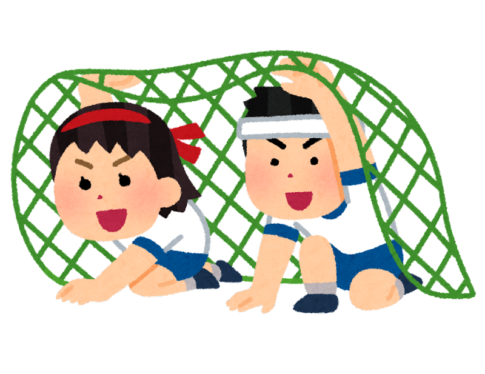




コメントを残す