はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をしているれんれんです📰
れんれん:
今日は新聞紙だけで大盛り上がりできる「新聞カーリング」を紹介するよ〜!
今日は新聞紙だけで大盛り上がりできる「新聞カーリング」を紹介するよ〜!
子どもたち:
えっ!?新聞紙でカーリング!?
転ばない?滑る?
えっ!?新聞紙でカーリング!?
転ばない?滑る?
れんれん:
実はね、工夫次第で安全に楽しめて、チームワークも身につく遊びなんだよ✨
実はね、工夫次第で安全に楽しめて、チームワークも身につく遊びなんだよ✨
📌【新聞カーリングとは?】
新聞紙を丸めてボール状にし、床に広げた的(ターゲット)に向かって滑らせるシンプルな遊びです。
誰でもすぐできる上、集中力・力加減・戦略性が楽しく育まれます!
👦【対象年齢・人数】
新聞カーリングは小学生全学年OK!
低学年はルールを簡単に、高学年は戦略要素を加えることで、幅広い発達段階に対応できます。
2人から始められますが、4〜6人のチーム戦にすると盛り上がり倍増!
📜【ルール】
- 新聞紙を1枚使って丸め、テープなどで固定した「新聞ボール」を作る
- 的(円形ターゲット)は床に描くか、マットなどで代用
- 交互に新聞ボールを投げ、中心に近い方がポイントGET!
- 中心ほど高得点にしたり、回数制や1発勝負などのアレンジも可能
🛡️【安全性】
新聞カーリングは接触・転倒のリスクが少ない安全な遊びです。
- 床が滑りやすい素材の場合はマットやラグを敷くと安心
- 投げるときは「人のいない方向へ」がルール!
- 遊ぶスペースは広めに確保して、机や角にぶつからないよう配慮しましょう
🌱【育まれる力】遊びながら学べる!
- 🎯 集中力:
的をよく見て投げる→結果を見る→次の一手を考えるという流れの中で、自然と“今ここ”に集中する習慣が身につきます。特に1回勝負やチームの代表として投げる場面では、子どもたちの集中力がぐっと高まります。 - 🧠 判断力:
「滑りやすい?」「勢いをつける?」「相手の球をよける?」など、場の状況を見て判断する力が育まれます。特に高学年では、「わざと外側から回す」などの戦略的な考えが生まれ、ゲームが知的に進化していきます。 - 🤝 協調性:
チームで順番や作戦を決める中で、「任せる」「応援する」「相談する」などの社会性・他者理解が深まります。勝敗にこだわりすぎず、みんなで楽しむ雰囲気作りも支援のポイントです。 - 🎨 創造力:
新聞紙の大きさや折り方、巻き方など、自由にアレンジできるからこそ、「自分だけの新聞ボールを作る」体験ができます。投げ方にも個性が出て、「こうやったらもっと遠くに行く!」という発見が楽しい学びになります。
🔧 学年別支援ポイント
- 低学年:
・新聞ボール作りは支援員が一緒に手を添えてサポート。
・「当たった!すごいね!」と結果より挑戦を褒めることが意欲に直結。
・的にシールやキャラマークを付けると、的当ての楽しさが倍増! - 中学年:
・記録表を用いて「何点だった?」「もっと近づくには?」と記録を振り返る流れを入れる
・作戦タイムでは、「どういう順番で投げる?」「どの的を狙う?」と役割分担やリーダー経験も意識できると◎ - 高学年:
・「相手の球を弾く」「得点2倍ゾーン」など高度なルールを導入
・「氷ゾーン(ツルツルした紙)」や「障害物(ティッシュ箱)」を置いてリアルなカーリング風の戦略性を育成
・振り返りシートを活用して、作戦の良かった点・改善点をチームで共有すると発表力や思考力にもつながります
🎉【おもしろポイント】
・新聞紙が意外な方向に曲がる!?毎回予測不能な展開に爆笑!
・「次は当てたい!」「チームで勝ちたい!」と熱中しやすく、リピート率◎
・子どもたちが「こんなルールもやってみたい!」と提案してくれることも多く、主体性を育てるきっかけにも!
🔗【関連記事】紙×遊びで大盛り上がり!
📚【まとめ】
新聞カーリングは、道具いらず&低リスクで始められる優秀レクリエーション。
遊びながら学びがあり、発達段階に応じた支援もしやすい万能あそびです✨
準備がカンタンなので、放課後クラブ・教室・雨の日レクにも大活躍!
ぜひ、子どもたちと一緒に新聞紙を丸めて、笑顔いっぱいの勝負を楽しんでくださいね♪
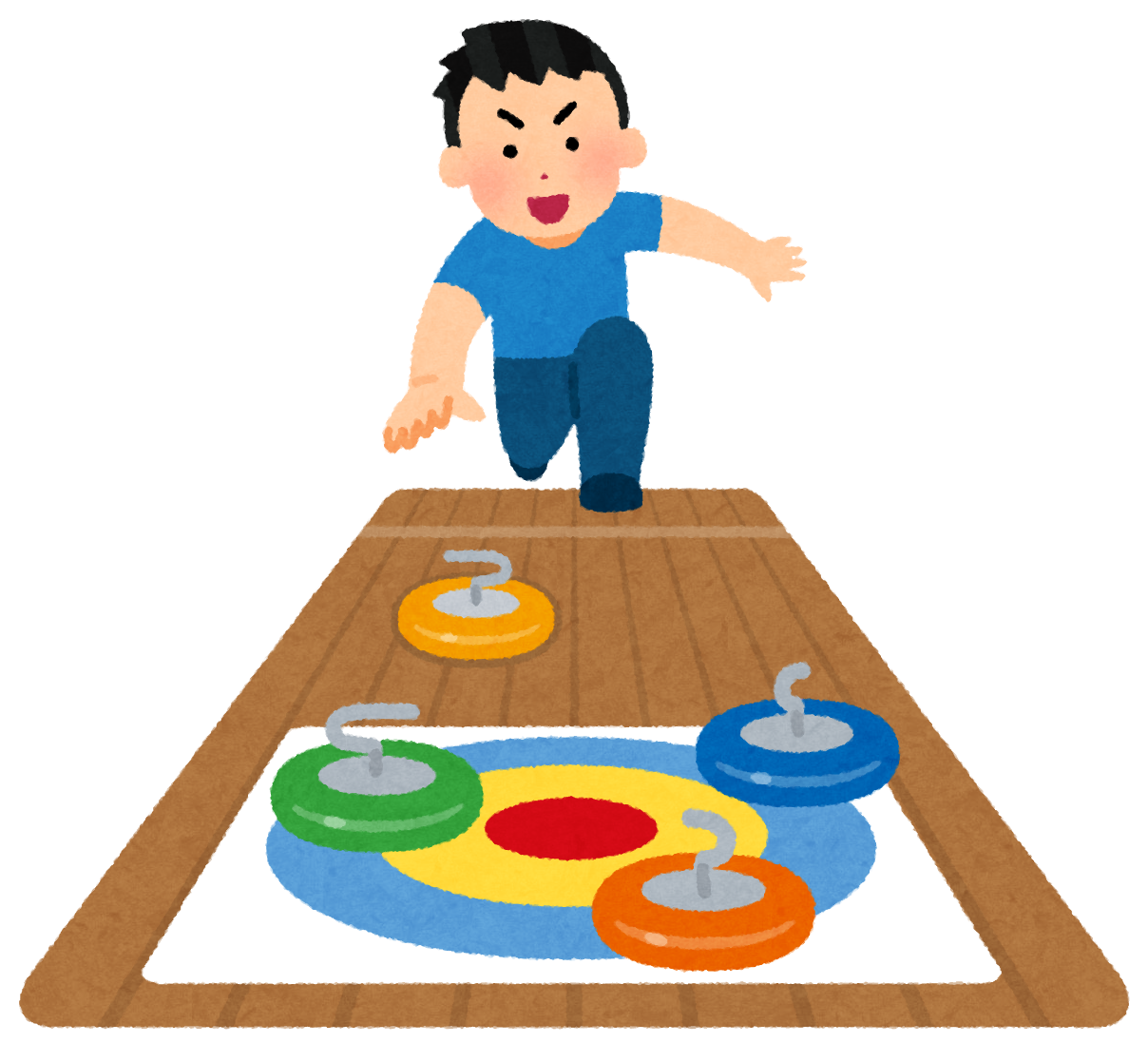








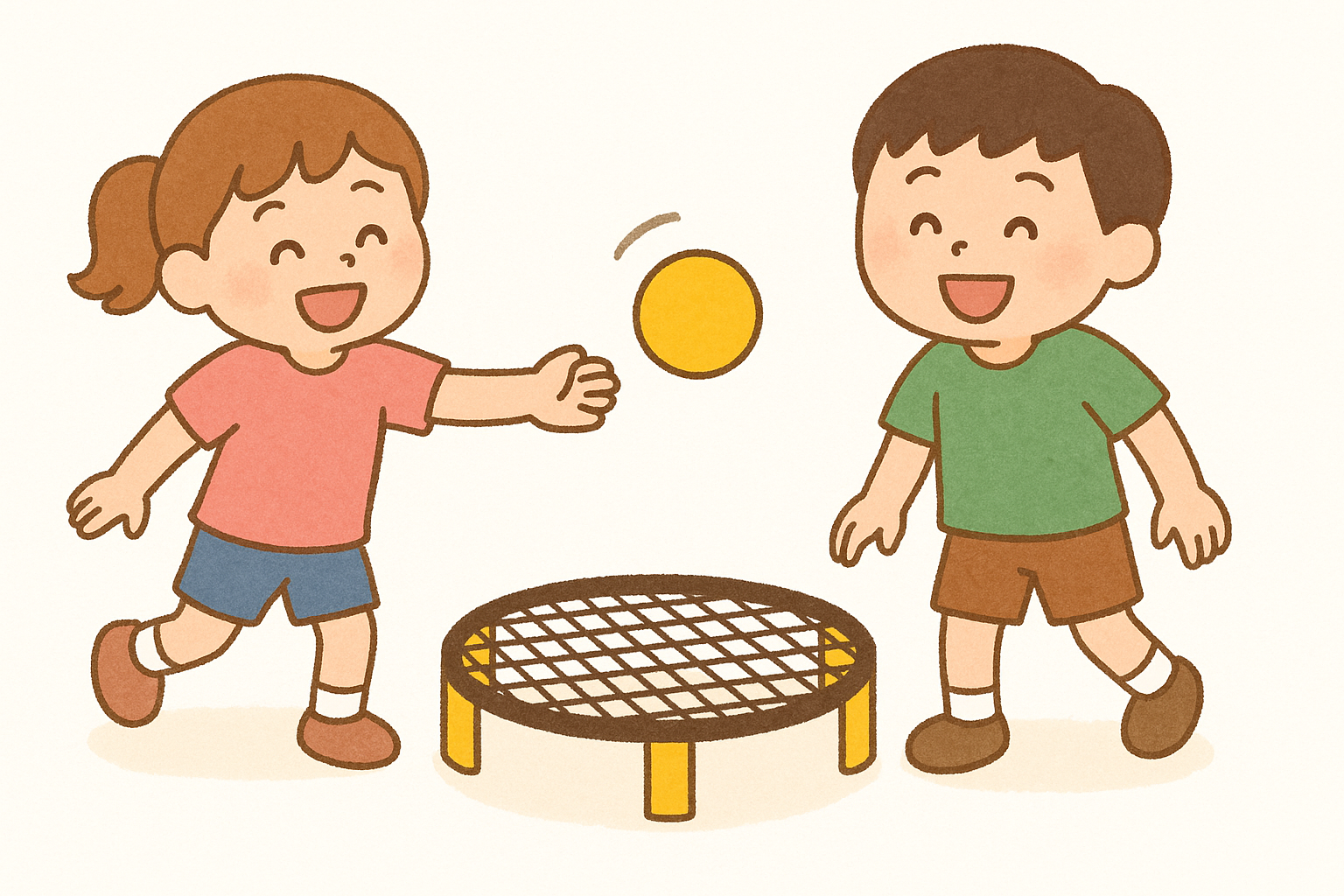
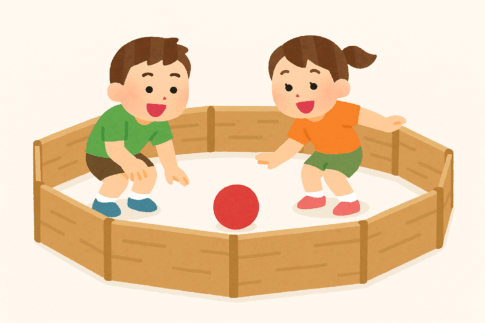





コメントを残す