はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をしているれんれんです!
放課後の時間、子どもたちが笑顔で過ごせる活動を探していませんか?
今回は、定番だけど奥深い!みんなで盛り上がれる「いす取りゲーム」をご紹介します。音楽に合わせて動く楽しさ、最後の1席をめぐるドキドキ感…。支援員としてのねらいや、安全面への配慮、年齢に応じたルール調整も含めて、わかりやすくお届けします!
[ad1]🎯 対象年齢と人数の目安
対象年齢:小学校低学年から高学年まで幅広く楽しめます。
人数:6人以上で可能ですが、10人以上だとより盛り上がります。
れんれん:人数が多すぎる時は、学年別グループに分けて同時進行もおすすめ!
📜 基本ルール
- いすは人数より1つ少なく用意し、円形に並べます。
- 音楽が流れている間、子どもたちはいすの周りを歩きます。
- 音楽が止まった瞬間に座ります。
- 座れなかった子はアウト。次のラウンドで1ついすを減らします。
- 最後の1人になるまで繰り返し、勝者を決めます。
🔄 ルールのアレンジ例
- 指令付きルール:「手を挙げてから座る」「逆回転にする」など動きに変化を。
- チーム戦:2チームで交互に挑戦し、座れた人数を競う方式もおすすめ。
- 音楽係の導入:高学年の子にBGM係を任せると参加感UP!
🔒 安全に楽しむために
椅子を巡って走る場面では、転倒や接触のリスクがあるため、以下の工夫を行いましょう。
- 滑らない床・広いスペースを確保する
- 角のある椅子にはクッションやテープで保護
- 最初に「押さない・ぶつからない」ルールを共有
れんれん:「ぶつからないように動こうね」と
繰り返し声かけすることで、遊びの中でも安全意識が育ちます!
🌱 育まれる力と発達段階に応じた支援(具体例つき)
いす取りゲームは、「ただ座るだけ」では終わりません!
子どもたちの身体的・社会的・認知的な成長に自然とつながる遊びです。
支援員は発達段階に応じて、声かけやルール調整でより深い支援が可能になります。
🧠 判断力
どの椅子に座るか、一瞬で状況を判断する力が育つ!
- 高学年には「自分がどこに立つと有利か?」「人の動きを見て先に動けるか?」など、
戦略を立てる思考力に働きかける声かけが◎ - 例:「次はどう動けば残れそう?」「椅子の近くにいられたコツってなに?」
🎯 集中力
音楽のリズム・ストップの合図に注意を向ける習慣が育つ!
- 低学年には「音楽が止まったらピタッと座る」というルールを、
視覚サイン(カード掲示など)や手拍子で補助するとスムーズ - 例:音楽係に合わせて「ピタッ!ってなったらすぐ座るよ~!」と事前に練習
🤝 社会性・協調性
負けたときの感情整理や、仲間と盛り上がる力が自然と育つ!
- 「座れなかったら次を応援する」「拍手をする」というルールを通じて、
勝ち負け以外の関わり方を学ぶ - 例:「応援隊長になってくれる?」「拍手してくれたの、うれしかったね!」
🌟 自己肯定感
「できた!」という達成感が、自信につながる!
- 小さな成功体験(座れた・拍手できた・音楽係ができた)を、
すぐに言葉でフィードバックすると、前向きな気持ちが続く - 例:「今のタイミングすごく良かったよ!」「自分でルール守れたね、かっこいい!」
🎉 おもしろポイント
・音楽が止まるスリルと、座れるかのドキドキ感!
・最後の1席をめぐる手に汗握る攻防戦!
・全員で一喜一憂しながら、全体が一体感をもてるのも魅力です。
子どもたち:もう1回やろう〜!
今度は勝ちたい!
📘 まとめ
いす取りゲームは、放課後の限られた時間でもサッと始められて、全学年の子どもたちが楽しめる万能レクリエーションです。
ルールのわかりやすさ、安全面の工夫、発達支援の視点を意識することで、より豊かな活動になります。
ぜひ、児童クラブや学童保育で取り入れてみてくださいね♪
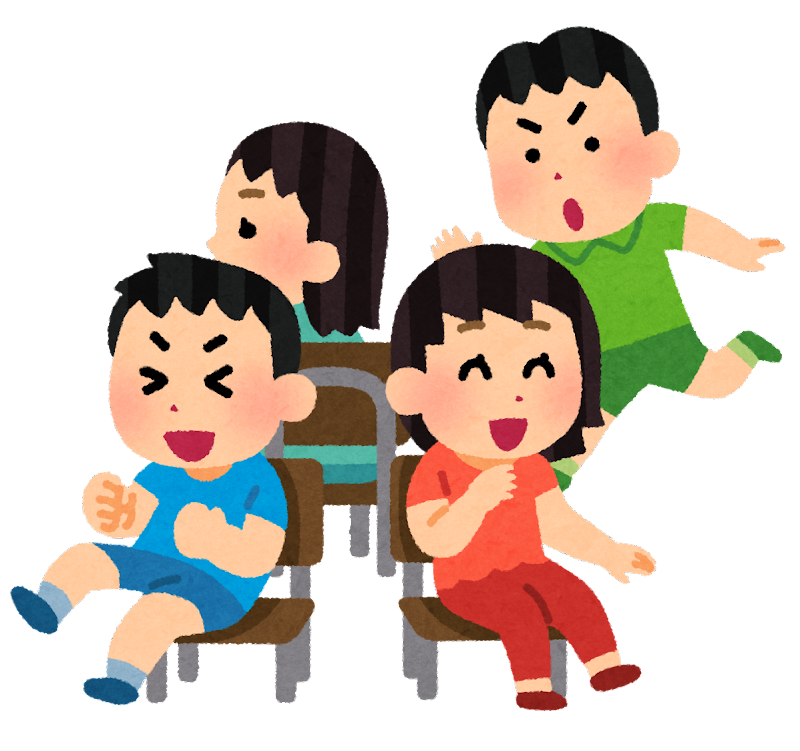


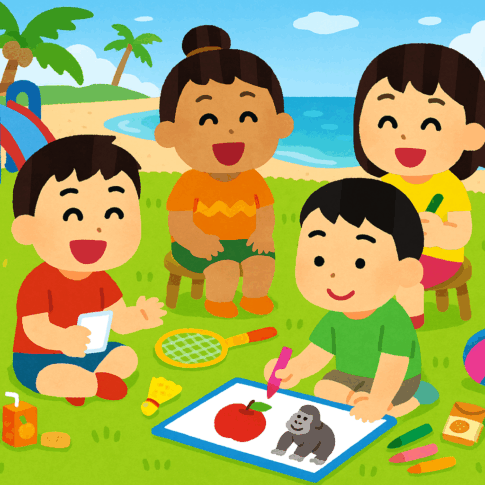












コメントを残す