れんれん:はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をやっているれんれんです!
今回は、私の児童クラブで子ども達と大盛り上がりだったリズム遊び「スーパーマリオゲーム」をご紹介します!
子どもたち:スイッチのマリオ!?やりたーい!
実はこれ、テレビゲームじゃなくて声とリズムだけで楽しめる、学童にぴったりの言葉あそびなんです!
みんなで笑って盛り上がれるうえに、集中力・記憶力・リズム感なども育つ、まさに一石四鳥の遊びですよ〜♪
🎯 対象年齢・人数・準備物
- 対象:全学年(低学年でもOK!)
- 人数:3名以上(5〜6人がテンポよくておすすめ)
- 準備物:なし!リズムと声だけで遊べます
📝 基本ルールと遊び方
- まず始める人を決め、時計回りに進めます。
- 「○○(名前)から始まるスーパーマリオゲーム!」の掛け声でスタート!
- みんなで「テレッテ テレッテ〜」とリズムを刻みつつ、順に「スー」「パー」「マリ」「オ」「スーパーマリオ」「コイン」と言葉をつなげます。
- 最後に「コイン!」で1周。次の周では「コイン」が2回、さらに次は3回…と増えていきます。
- 誰かが間違えたらアウト!負けた子は拍手で見送りつつ再チャレンジもOK。
🛡 安全対策
- 道具不要、体も動かさないのでケガの心配はほぼゼロです。
- 集中力が高まるので、静かな室内での実施がベスト。
🌟 得られる力
- 集中力:自分の番が来るまでの流れを聞き取り、タイミングを見極める力が育ちます。授業中の聞く力や、グループ活動でも活きる力です。
- リズム感:一定のテンポに合わせて発声することで、自然とリズム感が養われます。音楽・ダンス・発表活動にもつながる基礎づくりに。
- 記憶力:「スーパーマリオ」「コイン」の順番や回数を覚えることで、短期記憶力が鍛えられます。遊びの中で自然とトレーニングできます。
- 判断力・反応力:テンポが上がる中で自分の番を瞬時に判断し、反応する力が求められます。緊張感の中で冷静に対応する力にもつながります。
- コミュニケーション力:声をそろえたり、仲間と励まし合う中で、他者との協調性や一体感が育ちます。人間関係づくりの第一歩にも。
🧑🏫 支援員のねらい
- 年齢や発達段階に関わらず、誰でも「参加できた!」という実感が持てる遊びを通じて成功体験を積ませたい。
- リズムと言葉の遊びを通じて、学習に必要な耳の力(聞く力)や記憶力を楽しく育てる。
- テンポや難易度の調整がしやすいため、子どもたちの自己調整力やチャレンジ意欲を引き出すことができる。
👶 発達段階に応じた工夫
- 低学年:リズムが難しい場合は手拍子を添えてあげるとやりやすくなります。順番カードなどの補助も◎。
- 中学年:「コイン」の回数を増やすことで、記憶と集中のトレーニングに。テンポを少し速くしてゲーム性UP!
- 高学年:「スーパーマリオ」以外の言葉を取り入れて、自分たちでルールをアレンジしてもらうのもおすすめ。主体性や創造性を伸ばせます。
😆 支援員目線の楽しさポイント
れんれん:テンポが速くなると、大人でもついていけない時があって本気で悔しくなります(笑)
子どもたち:「やったー!先生に勝ったー!」と大喜び♪
単純なルールだけど、ゲームが進むと「スーパーマリオ、コイン×4」…と難易度もアップ!
リズムがバチっと合った時は、教室全体が笑顔に包まれるような一体感が生まれます。
年齢差があってもみんなで楽しめるので、高学年と低学年の交流にも最適な遊びです!
✅ まとめ|スーパーマリオゲームは室内OK!集中力と笑顔を引き出すリズム遊び
今回は、子ども達に大人気の「スーパーマリオゲーム」をご紹介しました。
マリオというワードに惹かれて、最初は興味本位で始める子も多いですが、ルールのわかりやすさとゲーム性の高さで、自然とのめり込んでいく姿が見られます。
準備物なしで室内でもOK!ちょっとした空き時間や雨の日レクにもピッタリです。
ぜひ、学童保育や放課後児童クラブ、学校のレクリエーションで取り入れてみてくださいね!
▼ 他にもこんな遊びがあります♪







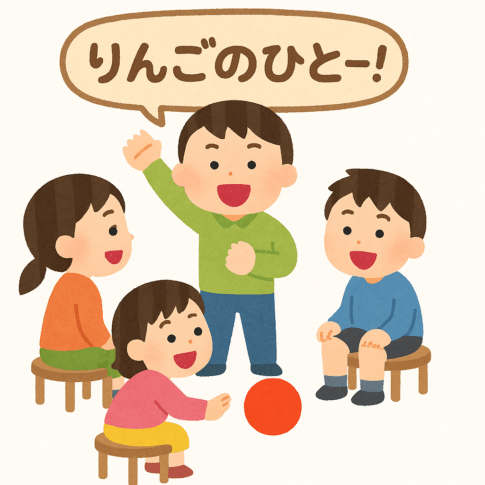

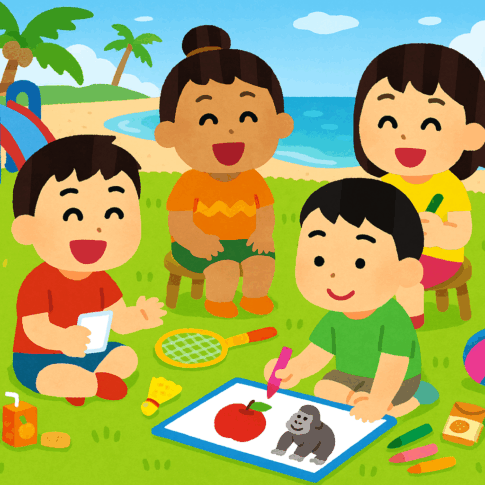






コメントを残す