「だるまさんがころんだ」― ドキドキと学びが詰まった定番鬼ごっこ!
れんれん:はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をしているれんれんです!
放課後の遊びで 集中力 と チームワーク を一度に鍛えられるゲームといえば、やっぱり「だるまさんがころんだ」。
シンプルなルールながら、子どもたちは “気配を消して進むスリル” に大盛り上がりです!この記事では、対象年齢・人数・ルール・安全対策・育まれる力・発達段階に応じた支援まで、支援員目線で詳しくまとめました。
子どもたち:先生!今日は誰が一番うまく止まれるか勝負しよう~!
🎯 対象年齢
小学校低学年(6歳)~高学年が目安。
低学年はルールを簡略化(距離短め・タッチ不要など)すると安心して参加できます。
👥 最適な人数
- 5~15人で円滑に進行
- 20人を超える場合は2グループに分けると待ち時間が減り集中が続く
📘 基本ルール
- 鬼役の「だるまさん」はゴールライン(壁や木など)に背を向ける。
- 他の子はスタートラインから少しずつ前進。
- 鬼が振り向きながら
「だるまさんがころんだ!」と唱えた瞬間、全員フリーズ。 - 動いた子を鬼が指摘できたらアウト→次回の鬼に。
- 誰かが鬼にタッチしたら「逃走タイム」。鬼はタッチした子の名前の文字数だけカウントし、逃げ切れたらタッチした子が勝利。
れんれん:タッチ後の逃走カウントは「イチ、ニー、サン…」と大きな声で!盛り上がり度MAX♪
🛡️ 安全面と環境づくり
- 地面が平らで障害物がない場所を選ぶ(屋外なら校庭の隅、屋内なら体育館)
- スタート~ゴールの距離は学年×10mが目安(例:2年生 → 約20m)
- 鬼の背面に壁があると安心。後ろ歩きで転倒しないよう配慮
- 「ぶつからない・押さない・ふざけすぎない」事前説明を徹底
🌱 育まれる力と発達段階に応じた支援
- 集中力|「ピタッと止まる」を意識する力
鬼の「だるまさんがころんだ!」の声に反応して、全身を一瞬で止める集中力が養われます。
🔸支援の工夫:
低学年には「止まる合図カード(🛑マークなど)」を活用し、視覚からも反応を引き出す。
声かけ例:「止まれたね!動きをピタッと止めるの名人だね!」 - 観察力|鬼の動きを“読む”力
「今、鬼の体がゆるんだぞ」「少し目をそらしてる!」など、相手の様子を観察して進むことで、人の動き・空気を読む力が育ちます。
🔸支援の工夫:
中学年には「どういうときに鬼は油断しやすいか?」など、作戦会議タイムを入れることで観察の視点を持たせる。
声かけ例:「あのときの鬼の肩の動き、気づいた?観察バッチリだったね!」 - 判断力|動く・止まるを瞬時に選ぶ力
進むタイミングや立ち止まる判断を自分でコントロールする場面が多く、状況に応じた自己判断が育まれます。
🔸支援の工夫:
高学年には「ペアを組んで“安全なルート”を考える」など、戦略的判断の場面を取り入れると効果的。
声かけ例:「今の進み方、自分でタイミング選べたのすごいね!」 - 協調性|仲間と関わりながら進む力
「今だよ!」「次は○○が鬼ね!」など声をかけ合い、仲間と役割を共有することで、関わる力が養われます。
🔸支援の工夫:
全学年共通で「鬼は毎回交代制」「一度も鬼をやってない子にバトンタッチ」など、公平なルール設計で関わりの機会を増やす。
声かけ例:「交代ありがとう!次にやってみたい子が安心できたよ〜」 - 自己肯定感|達成体験を通じて得られる自信
「うまく止まれた」「タッチできた」「鬼役を堂々とできた」など、成功の瞬間を支援員がすくい取って言葉にすることで、自己肯定感が育ちます。
🔸支援の工夫:
特に人前での行動が苦手な子には、小さな挑戦でも即座にポジティブなフィードバックを。 声かけ例:「鬼やるって手をあげたね、すごいチャレンジだったよ!」
れんれん:子どもたちの行動を“育ちの種”として見つけてあげると、遊びの価値がもっと深まりますよ〜!
🎉 おもしろポイント
- 鬼が振り向く瞬間の“心臓バクバク”がクセになる!
- タッチ→逃走タイムの一発逆転劇で大歓声
- 声色やテンポを変える“アレンジ鬼”で爆笑必至
🔚 まとめ
「だるまさんがころんだ」は、少人数でも多人数でも、そして道具なしで楽しめる万能レクリエーション。
集中力・観察力・協調性など多面的な力を養いながら、子どもたちの笑顔を引き出します。
安全な環境と発達段階に合わせた声かけで、ぜひ日々の学童活動に取り入れてみてください♪




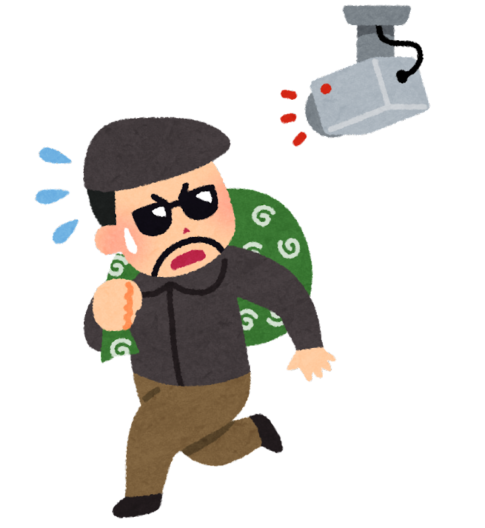
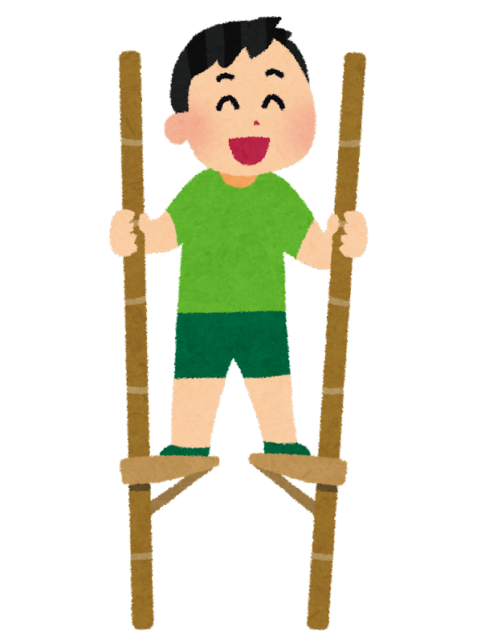










コメントを残す