はいさい!沖縄で児童クラブ支援員をしているれんれんです♪
今回は、ホラーゲームでおなじみの「青鬼」をモチーフにした、子ども達に大人気のレクリエーション「青鬼ごっこ」をご紹介します!
「あのYouTubeで見る青鬼の遊び!?」と、初めて聞いた子ども達は大興奮。中には「怖いの苦手…」という子もいましたが、ルールを工夫することで誰でも楽しく遊べるようになりました♪
🎯 対象年齢
小学生全学年におすすめです!
ルールも簡単で、低学年もすぐに覚えられます。
👥 人数
3人以上いれば遊べますが、6人以上だとより盛り上がります。
🎒 準備物
- 青色のコイン(紙・シール・カードなど)
- 復活カード(トランプや折り紙でも代用可)
- スマホやスピーカー(青鬼の出現音を流すと雰囲気アップ)
🎮 基本ルール
- 制限時間:15分
- 準備時間:3分(青鬼が隠れる時間)
- 逃走者はコインを探し、青鬼から逃げる
- コインをすべて見つけたら逃走者の勝ち
- 捕まったら脱落、復活カードで1回復帰可(任意)
- 全員が捕まれば青鬼の勝ち!
🔄 応用ルール例
- 青鬼を2人に増やす(人数が多いときにおすすめ)
- コインの場所をヒント制にする(例:カードに「2階にあるよ」など)
- 音でドキドキ感UP:出現音で青鬼が動き出す、など
⚠️ 安全面の配慮
青鬼が突然現れる演出はとても盛り上がりますが、驚いて転んだりぶつかったりする危険もあるので、次の点に注意しましょう。
- 室内なら走らず「早歩き」や「スキップ」までに制限
- 階段・段差には立ち入らせない
- 青鬼役はできれば職員や高学年が担当
🧠 この遊びで育つ力
「青鬼ごっこ」はただ逃げるだけの遊びではありません。子ども達はこの遊びを通して、考える・感じ取る・伝える・判断するといった力を自然に育んでいます。
遊びの中で「どうしたらうまくいくか?」を考えたり、怖さや不安を乗り越えたりする経験は、学校では学びにくい“生きる力”につながる大切なプロセスです。
支援員として見ていても、いつも控えめな子が「こっちに逃げて!」と仲間に声をかける姿など、遊びの中での“成長の瞬間”がたくさん見られました。
🗣 遊んでみた感想と工夫
実際に青鬼ごっこをやってみて、子ども達のテンションは最高潮!
特に「大人が青鬼」になると、子ども達は本気で逃げ回って大盛り上がり。大人側もつい笑ってしまうくらい楽しい遊びです。
コインの隠し場所は、「ちょっと見えていて、でも取りにくい」くらいがちょうどいいです。怖がりな子でもチャレンジしやすくなります。
スマホで「青鬼の出現音」を流すと、緊張感とリアル感がUP!
📣おすすめ出現音リンク:こちら(YouTube)
📝 まとめ
今回は、ホラーゲーム「青鬼」を題材にした新感覚レクリエーション「青鬼ごっこ」をご紹介しました。
子ども達の間で人気の題材を使った遊びは、親しみやすさと新鮮さのバランスが取れていて、大盛り上がり間違いなしです!
遊びの中には、伝える力・考える力・動く力が自然と育つヒントがたくさん。ぜひ、放課後クラブやレク活動で活用してみてください♪
👻 他にもおすすめの鬼ごっこを紹介中 → 鬼ごっこ特集はこちら
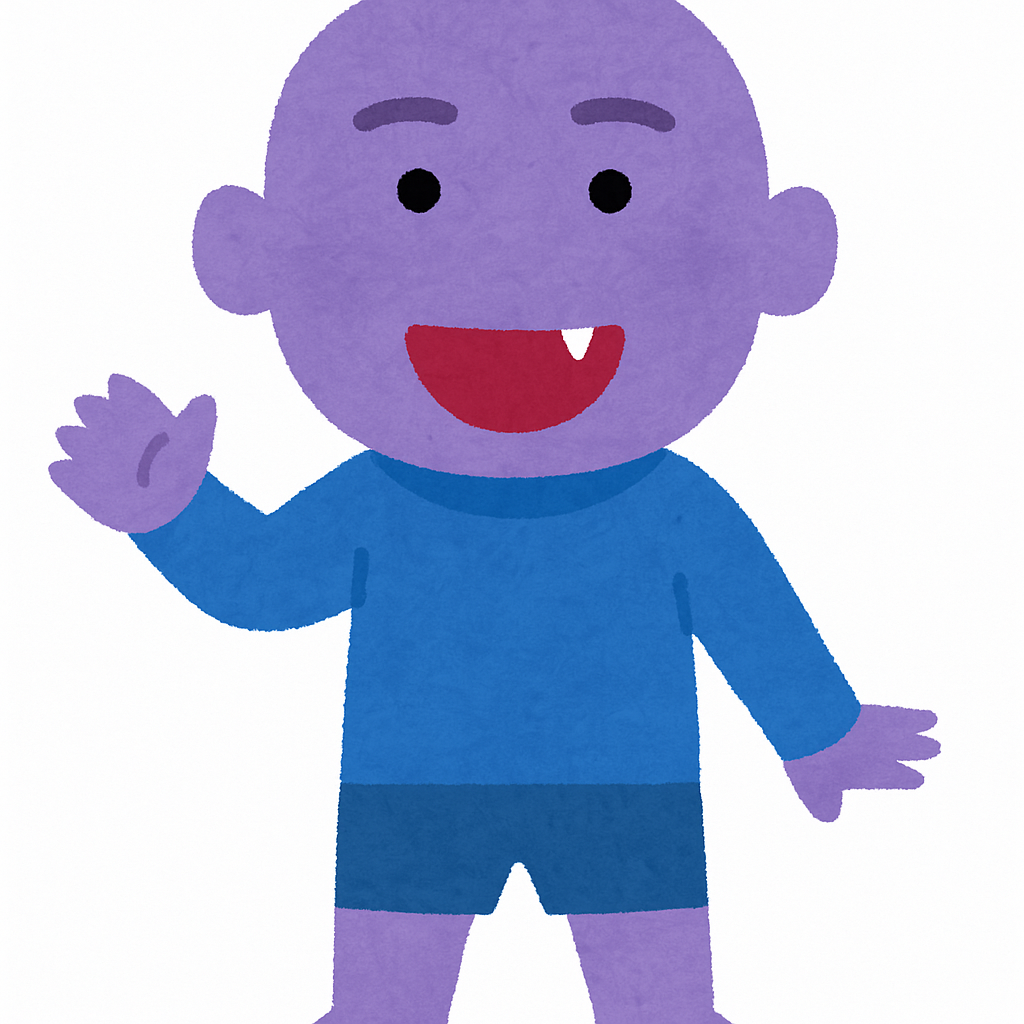
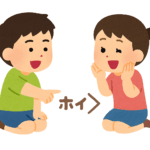






コメントを残す